Published on
日本 - ベナン相互協力 日本人2名がベナン共和国国歌を歌う(2006/12)
12月初め、たけし日本語学校日本語教師の2名が、ベナンのウェブニュース、La Citadelle(ラ・スィタデル)の写真に掲載されました。本文がフランス語なので、日本語に翻訳、修正し、本文のみ掲載します。

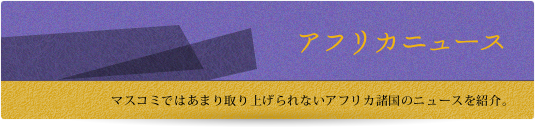
December 2006 の記事一覧
Published on
12月初め、たけし日本語学校日本語教師の2名が、ベナンのウェブニュース、La Citadelle(ラ・スィタデル)の写真に掲載されました。本文がフランス語なので、日本語に翻訳、修正し、本文のみ掲載します。
Published on
ジャーナリストを守るNGOの「国境なき記者団(本部、パリ)」が今月発表した「報道の自由度指数」で、ベナンが23位となり、アフリカで最も報道しやすい国と評価した。アフリカ内2位と3位はそれぞれ、ナミビア(全体で26位)、モーリシャス(全体で32位)だった。04年の指数では、南アフリカが26位で、アフリカ内1位。ベナンはその次の27位、アフリカ内で2位だった。05年では、ナミビア、キプロスと並んで25位。ナミビアと並んでアフリカ内1位だった。
また、今年はガーナの順位が、昨年66位から34位と飛躍的に上昇した。ガーナメディアに対する経済状況は依然として困難な状態にあるものの、他の権力者や権威集団からの危険にさらされなくなったことを評価している。
ちなみにこの指数で、日本は51位、アメリカは53位、ロシアは147位と、主要先進国の中で報道しにくい3カ国となった。
さらに、エリトリア(166位、アフリカで最下位)、トルクメニスタン(167位)、北朝鮮(168位、全体で最下位)がワースト3とされた。エリトリアは、5年以上無実の罪で投獄されたジャーナリストが数名いたことが、トルクメニスタンは、ニャゾフ大統領に対する批判的な報道を抑圧したことが、北朝鮮は、金正日総書記が継続してメディアをコントロールしていることが、それぞれこのような順位になった要因とされている。
Published on
「アフリカのニュース」といっても範囲が広すぎていろいろあると思います。取り上げる内容もさまざまだと思います。しかしながら、日本のマスコミの多くは、アフリカ関連のニュースのほとんどを、内戦、飢餓、貧困、未開、野蛮などといった言葉に関連するような視点で取り上げることが多いように思います。確かに、統計で見れば、アフリカ地域は世界の中でも内戦や飢餓、貧困は多いのは事実です。だからといって、それ以外の内容を報道しないからというのは、いくら視聴率や協賛の問題があるとはいえ、マスコミとしての機能を十分に果たしていないのではないでしょうか。
特にテレビに関して申しますと、子供に与えるインパクトはあまりに大きく、テレビで見たものが、イコールアフリカと思ってしまう構造を作っているように感じられます。アフリカには53もの独立国があり、それらの政治形態や社会は、それぞれが似ていながらも違うところが多いものです。にもかかわらず、国の名前をあまり取り上げず、アフリカというひとくくりの中に、ある種日本が文明国で、テレビで取り上げたアフリカの国や地域が野蛮な後進国であるという、一元的な印象を与えているようにしか思えません。
さらに問題なのは、義務教育や高等学校などでのアフリカに対する教え方です。ご存知のとおり、アフリカが教科書に登場する分量は、ほかのアジアや欧米のものよりもわずかで、概要的な内容が多いものと思います。内容自体も、南アフリカのアパルトヘイト、各種地下資源、砂漠化や貧困といったトピックが多いものでしょう。歴史に関しても、本格的に登場するのは奴隷貿易が始まった16世紀からであり、それまでの歴史情報は決して充実したものとはいえないでしょう。そのような背景で勉強してきた先生方が現に今アフリカに関して教えているのですから、先生方もアフリカについて偏った知識しかもってなく、それで生徒に教えるというのですから、充実したアフリカ教育は不可能だと思います。現に私がお世話になった先生方も、アフリカ諸国の国の名前、例えばブルキナファソを知らない先生がいたりするものです。
そこで、このコラムでは、これらマスコミではあまり取り上げられないアフリカ諸国のニュースを、それも明るく、専門家やアフリカ好きの方しか知らないようなマニアック物を取り上げていきたいと思っております。一元的な日本人の持っているアフリカのイメージを、このコラムから二元的、三元的になっていき、日本とアフリカ諸国の文化交流のきっかけになれば、この目的は達成したといえるでしょう。
これからアフリカに対して、政府や民間企業が投資していく機会が増えていくでしょう。最近は韓国や中国がエネルギー資源の採掘権などの分野でアフリカ諸国に参入していくこともあって、ますますアフリカに対する知識・関心は増えていくことと思います。
(文責:山瀬靖弘)